宇宙エレ体験教室@山梨県立科学館 ― 2010/11/13

鬼が笑う来年の話。
来年早々、1月15日と16日、山梨県立科学館で宇宙エレベーター体験教室が大々的に開催されます。
こちら。
現在の企画では、ゼロからオリジナルの宇宙エレベーターを作る体験教室の他にも、ある程度完成したボディにオリジナルの装飾を加えて昇降を楽しむ体験、純粋にクライマーの昇降を楽しむ体験など、年齢や許される時間に合わせていくつかの体験コーナーを設ける予定。
私は「ゼロからオリジナルの宇宙エレベーターを作る体験教室」の部分の講師を務めます。
山梨県、近県にお住まいの方のご来場をお待ちしています。
開催日近くになってきたら、またお知らせします。
レゴと犬吠埼と風向風速計 ― 2010/11/15
LEGO punch! ― 2010/11/16
去年あたりから発売されている「レゴブロック穴パンチ」と「カラーペーパーパッド」を買ってみた。
製品情報はこちら。
カラーペーパーパッドには、カラフルな厚めの紙に加えて、上のような穴定規が付いている。(これで980円はチト高いのでは‥)
穴を開けてみた。普通のオフィスにあるパンチの穴は直径6mm。対してレゴブロック穴パンチの直径は5.1mm。僅かに小さい。この穴にポッチがピッタリ入る。
ちなみに、上の写真の黒い方は、以前、香川県の「e-とぴあ・かがわ」のイベント用に製作したローバーのパネル。これは普通の6mmのパンチで穴を開けた。
青い方は、レゴ社の7471「Mars Exploration Rover」に入っているパネル。穴は6.3mmぐらいある。
紙や樹脂は温度や湿度で伸び縮みする。たとえば、プラスチックのシートにキッチリ16ポッチの間隔で穴を2つ開けたとする。でも、それがいつも16ポッチの間隔とは限らないのだ。その変化を吸収するために、穴に少しの余裕が必要となる。だからレゴ社純正のパネルでも、穴の直径をポッチピッタリの5.1mmにはしていないのである。
もちろん1ポッチ2ポッチぐらいの飾り物を紙や樹脂で作るときは、5.1mmの穴が「ピッタシ」で気持ちいい。でも、上記のパネルのようなものを作るときは6mmパンチを使うことをおすすめする。つまり、上手に使い分けましょう − という話なのだ。
LEGO punchで紙あそび ― 2010/11/17
「レゴブロック穴パンチ」の作品。
一般的な作例は、「ここ」にたくさん掲載されている。
私が同じ路線で作例を載せてもしかたがないので、レゴブロックを「機能性を高める部品」として「折り紙」とコラボしてみた。まず「紙飛行機」。
折り紙で紙飛行機を作る − ほとんどの方が経験していると思う。
ポイントは「どのようにして前部を重くするか」である。普通は、紙を何回か折り返し、その重さを作り出す。ただし、重すぎるとすぐに頭から落ちるし、軽すぎると落ち葉のように舞ってしまう。ちょうど良い重さにたどり着くまでに、折り返しの幅や回数を変えて試行錯誤を繰り返す。
その重さの調整をレゴブロックでやってしまおう、というのが、上の写真の飛行機。
折り紙は2ヶ所折っただけ。コックピットの位置にパンチでポン。
一度目のチャレンジはこれ。1ポッチラウンドプレート2つ。
投げ方によってはうまく飛ぶが、舞ってしまうことの方が多い。
2ポッチ長のシャフトとハーフブッシュ2つの組み合わせ。
さっきのものより、ずっときれいに飛ぶ。
なんだかんだ、パーツを取っ替え引っ替え、結構楽しい。
みんなで集まって飛ばしっこするのも一興かと。(^_^)
LEGO punchで風車 ― 2010/11/18
今度は風車。
これも多くの人が製作体験していると思うが、一番面倒なところは支点(回転軸)の部分の処理。千枚通しで穴を開けて、粘土かビーズか何かでストッパーを付けた竹ひごを差し込んで、さらに留める‥。さらにそれを立てるスタンドで悩む‥。
「レゴブロック穴パンチ」を使えば至極簡単。中心にポン。(右の風車はさらに4枚の羽の先端にポン)
あとは、レゴブロックのシャフトを差し込んで、ブッシュなどで留めれば完成。
裏はこんな感じ。
角度もデザインも自由自在。微風でもよく回る。
なお、通常のパンチの使い方だと、紙の端から1cmぐらいのところまでしか穴を開けられないので、折り紙の中心にパンチすることは不可能。紙を半分に折って、半円パンチで解決する。
キラキラeneloop ― 2010/11/20
キラキラのeneloopが来た。
製品情報はこちら。
Power Functionで単4のニーズが出てきたなぁと思いきや、eneloopのカラーバージョンにも単4が追加され「ああ、これは買うしかあるまい‥」状態。
以前の記事「からふるeneloop」で紹介したように、充電池を同色6本単位で管理できるのはとても便利かつ効率的であることを実感している。だから今回も6セットずつの購入。
まんまとサンヨーのワナに引っかかっているような気もするが‥。(^_^;)
2011年のレゴテクニック ― 2010/11/23
毎度おなじみの来年セットのリーク画像。
まずは、このページをご覧いただきたい。
4枚目の写真に見慣れないパーツが写っている。
新しいリニアアクチュエーターか?
しかし、この形状で一体化されているなら、チト使いにくそう気もするが‥。
さて、来年を楽しみに待とう。
レゴ製スペーサー ― 2010/11/25
これは、作品を撮影するミニスタジオの背面床部分。奥にあるテーブルタップから撮影用ライトに電源が供給されている。
ここでは、レゴブロックがスペーサーとして地味ながら活躍している。
単に4×8プレートの上に2×8ブロックを何段か積んだだけのもの。向こうの端っこにも同じものが置いてある。これがあることでテーブルタップへの横からの圧力を回避できる。(実はこのミニスタジオの台は大きな「引き出し」なので、引出しを閉めるたびにガツンガツン背面に圧がかかるのである)
「レゴブロックは作品を作るものだ」という信念を持つ方にとっては、これは冒涜とも言える使い方かもしれない。(^_^;)
私自身にとってレゴブロックはあくまでも素材でしかない。ときには、それを使って「作品」と呼べるものまで昇華させるし、ときには素材に近い状態のまま便利に利用する。大きさや形、色が自由で、何度でも試行錯誤できる素材って他にないしね。このスペーサーだって、木片で作ろうと思ったら寸法を測って、切って、ペンキで塗って、乾かして‥ と想像するだけで面倒だ。
風力電車公開 ― 2010/11/27
ファンを回して風を起こし、それを推進力として走る電車。
こちら。
上記記事でも書いてあるが、目玉は新しい構造のファン。
強くて方向性の高い風が起こる。
実はこの作品を作る過程で、単4のバッテリーボックスや、同サイズのトレイン用リチウムポリマー充電池などを試用してみた。しかし、どんどんどんどんどんどん加速していき、最終的には必ずカーブで脱線横転。だからといってギア比を減らして風を弱めればこの新型ファンのポテンシャルがもったいない。なので、あえてeneloop単3電池×6本の最重量級のバッテリーを組み込んで走らせた。
いろいろ試行錯誤をしながらおもしろいことに気付いた。ファンの位置は低すぎるとだめなのだ。線路スレスレの高さまでファンの位置を下げると、推進力が弱くて進まない。空気はファンから後方に円錐状に吹き出されるから、ファン位置が低いとその円錐が床で切取られてしまって推進力が弱まるのではないかと想像している。
パーツ考察 − 36【電池重量】 ― 2010/11/30
先日の風力電車の記事で、「eneloop単三6本で最重量級」と記載した手前、普通の電池や他のバッテリーボックスに比べてどのくらい重いのか、きちんと測ってみた。
上記の「単三バッテリーボックス」は電池が入っていない状態で、53.17g。
eneloopの単三は 25.93g。乾電池(IKEAブランド)は 22.65g。
それぞれ6本ずつ入れるとこうなる。
53.17+(25.93×6)=単三バッテリーボックス+eneloop:208.75g
53.17+(22.65×6)=単三バッテリーボックス+乾電池:189.07g
次は、「単四バッテリーボックス」。空の状態で39.46g。
eneloopの単四は 11.71g。乾電池(IKEAブランド)は 11.35g。
それぞれ6本ずつ入れるとこうなる。
39.46+(11.71×6)=単四バッテリーボックス+eneloop:109.72g
39.46+(11.35×6)=単四バッテリーボックス+乾電池:107.56g
39.46+(11.35×6)=単四バッテリーボックス+乾電池:107.56g
さいごに単四バッテリーボックスと同サイズのリチウムポリマー充電池。
リチウムポリマー充電池:74.76g
さすがに軽い。
簡単なまとめ。
eneloop入りの単三バッテリーボックスを基準に考えると、
・電池を乾電池に変えると、約1割軽くなる。(ただし乾電池の種類による)
・単四バッテリーボックスに変えると、約半分の重さになる。
・リチウムポリマー充電池に変えると、約1/3の重さになる。
個人的には、徐々に単四バッテリーボックスに移行していきたい気持ちだが、まだまだ入手が難しい上に割高なんだなぁ。BrickLinkでも、単三バッテリーボックスの3倍のお値段だし。
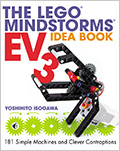

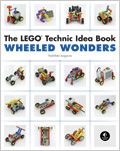
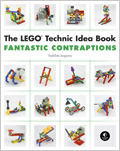























最近のコメント